
こんにちは。扇町漢方クリニックの院長、大沢です。
「体質別セルフケアシリーズ」第5回は、《湿痰(しったん)》タイプです。
「朝から体が重い…」
「むくみやすく、痰や鼻水が多い」
「頭がボーッとしてやる気が出ない」
こんな不調が気になる方は、《湿痰体質》かもしれません。
漢方では、体の中に余分な“水分”や“不要なもの”が溜まった状態を「湿痰(しったん)」と呼びます。
この記事では、湿痰の特徴や原因、体をスッキリ軽くするセルフケア法をご紹介します。
◆湿痰とは?~余分な“水分”が体にたまった状態~
身体の中にある水のような存在を「津液(しんえき)」と言います。
「津液」は、「脾(消化器系)」の働きで食べ物から吸収されて作られます。
そして「肺」に運ばれて、「肺」から一部は体外に放出されますが、残りは全身にシャワーのように散布されます。
たくさん飲み食いすると「津液」が大量に吸収され、その分「肺」に運ばれます。
大量の「津液」は「肺」の働きに負担をかけて悪くします。
その結果、「津液」がうまく散布されなくなり停滞します。
過剰になったり停滞したりしている「津液」は余分な役に立たない「湿」となります。
さらに「湿」が固まって粘り気があるものを「痰」と言います。
この「痰」は、肺や気管支にたまるだけでなく、身体中どこにでも発生します。
漢方でいう「痰湿(たんしつ)」は、体の中にたまった“余分な水分”や“老廃物”のこと。
この「湿」がたまりすぎて巡らなくなった状態が、「湿痰(しったん)」体質です。
本来であれば、汗や尿、便などとして外に排出されるべき水分が、うまく出ていかずに体の中に停滞してしまうのです。
◆湿痰タイプの主な特徴
次のような症状に心当たりはありませんか?
・朝から体が重だるい
・頭がボーッとして集中できない
・むくみやすく、特に下半身が重い
・痰が絡む、鼻水が出やすい
・胃がもたれる、食欲がない
・便がゆるい、軟便・下痢気味
・舌に白くてべったりした苔がある
この体質の方は、例えるなら「湿気の多い梅雨の日のような体の状態」
ジメジメとした重さを感じやすく、やる気が出にくくなります。
◆湿痰の原因になりやすい生活習慣
体に湿がたまる背景には、以下のような要因があります。
・冷たいものの摂りすぎ(アイス・生野菜・冷水など)
・脂っこいもの・甘いもの・果物の過食
・胃腸の弱さや疲れ(消化・吸収・排泄の力が弱い)
・運動不足による代謝の低下
・高温多湿な気候(日本の梅雨や夏など)
つまり「入ってきすぎる」「出ていかない」「めぐらない」の三重苦。
体が “水はけの悪い土地” のようになっている状態です。
◆今日からできる!湿痰のセルフケア
湿痰体質のケアでは、「水分代謝を助けて、巡りをよくする」ことが大切。
胃腸を元気にして“出せる体”をつくっていきましょう。
①胃腸を冷やさず、温めて整える
湿痰体質では、まず胃腸を守ることが最優先。
胃腸が弱ると、余分な湿がどんどん溜まりやすくなります。
おすすめの食事
- 温かいスープ・おかゆ・蒸し野菜など
- 消化のよい食材(山芋、白身魚、豆腐、かぼちゃなど)
- あずき、えんどう豆、そら豆、アスパラガス、唐辛子、なずな、まいたけ
- 香味野菜(しょうが、ねぎ、大葉)
- あさり、あゆ、こい、こんぶ、どじょう、なまず、のり、はまぐり
- 鴨肉、豚レバー
反対に、冷たい飲み物・果物・生野菜・乳製品・揚げ物・甘いものは控えめに。
②水分は「とりすぎず」「ためこまず」
「湿があるなら水は控えるべき?」と思う方もいますが、ポイントは“出せる体”をつくること。
ただし、「冷たい水をがぶ飲み」するのはNG。
- 常温か白湯を、こまめに少しずつ
- 利尿作用のあるお茶(はとむぎ茶、とうもろこしのひげ茶など)を活用
- 汗をかく程度の軽い運動や入浴で排出を促す
③体を動かして「湿」を追い出す
汗をかくことで、体内の湿を外に出すことができます。
- ウォーキングやストレッチなどの軽い運動
- 半身浴でしっかり温めて汗をかく
- ふくらはぎのマッサージで水の巡りを助ける
湿痰体質の方は、「ゆるく・こまめに動く」ことが体調管理のコツです。
④体にたまった“湿と痰”を取り除く漢方薬の考え方
湿痰体質では、体の中に「余分な水分(湿)」や「老廃物(痰)」がたまりやすく、それが体の重だるさや、めまい、むくみといった不調につながります。
中医学では「燥湿(そうしつ)」や「化痰(けたん)」と呼ばれる処方を用いて、余分なものを排出し、体を軽くすることを目指します。
半夏白朮天麻湯(はんげびゃくじゅつてんまとう)
→ 胃腸の機能(脾の働き)を助けながら、痰を取り除き、頭部のめまいやふらつきを改善する処方です。
特に、「水分の代謝が悪く、頭が重い」「めまいがしやすい」という方に使われます。
脾虚湿盛(ひきょしっせい)と呼ばれる、胃腸の弱りに由来する湿痰のタイプに適しています。
平胃散(へいいさん)
→ 胃腸にたまった湿(=“胃の中の余分な水分”)を取り除く基本処方です。
食べすぎや飲みすぎで胃が重たい、ガスがたまりやすいといった「飲食過多型の痰湿」に適しています。
防己黄耆湯(ぼういおうぎとう)
→ 全身に湿がたまってむくみや関節の重だるさがある人に使われます。
いわゆる水肥りタイプの人に対して全身の停滞している水を巡らす効果が期待できます。そのため肥満症、多汗症などの改善につながります。
余分な水の停滞が解消されることで、関節部位の水も巡って関節の痛みや腫れがとれたりします。
ただ、水の巡りの原動力となる「気」の巡りに作用するものが含まれていないので、他の漢方薬を併用することはよくあります。
湿痰体質は、脾(消化器系)の機能が弱っていることが多く、根本的には「胃腸を元気にする」ことが改善のカギとなります。
◆湿痰タイプへのメッセージ

湿痰体質の方は、身体が重く感じられて、思うように身体が動かず、もどかしい気持ちになることも。
体も心も“めぐってこそ”元気になります。
体を冷やさず、溜めこまず、少しずつでも「流れのある生活」に切り替えていきましょう。
心と体がスッと軽くなる感覚を、あなた自身ので取り戻していけるはずです。
次回は「湿熱(しつねつ)タイプ」についてご紹介します。
「ニキビ・口臭・おりものが気になる」
「体が熱っぽくベタベタする」
…そんな不快感がある方は、ぜひご覧ください。


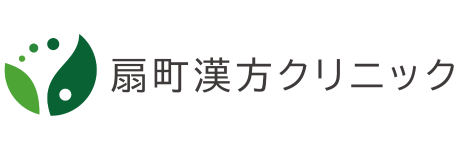
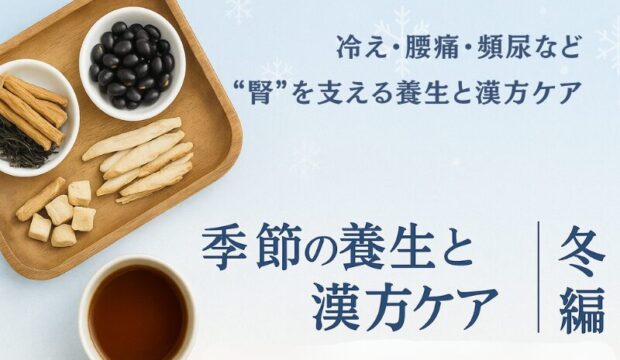


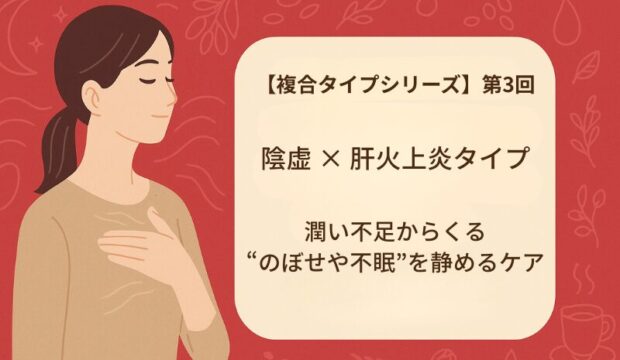
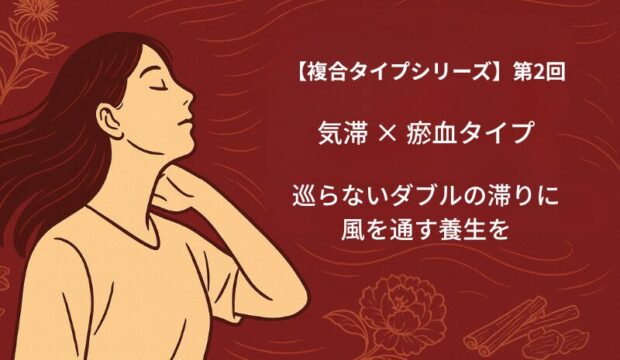








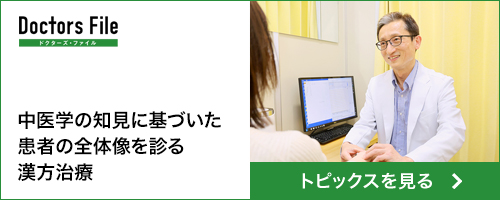
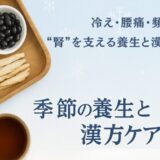








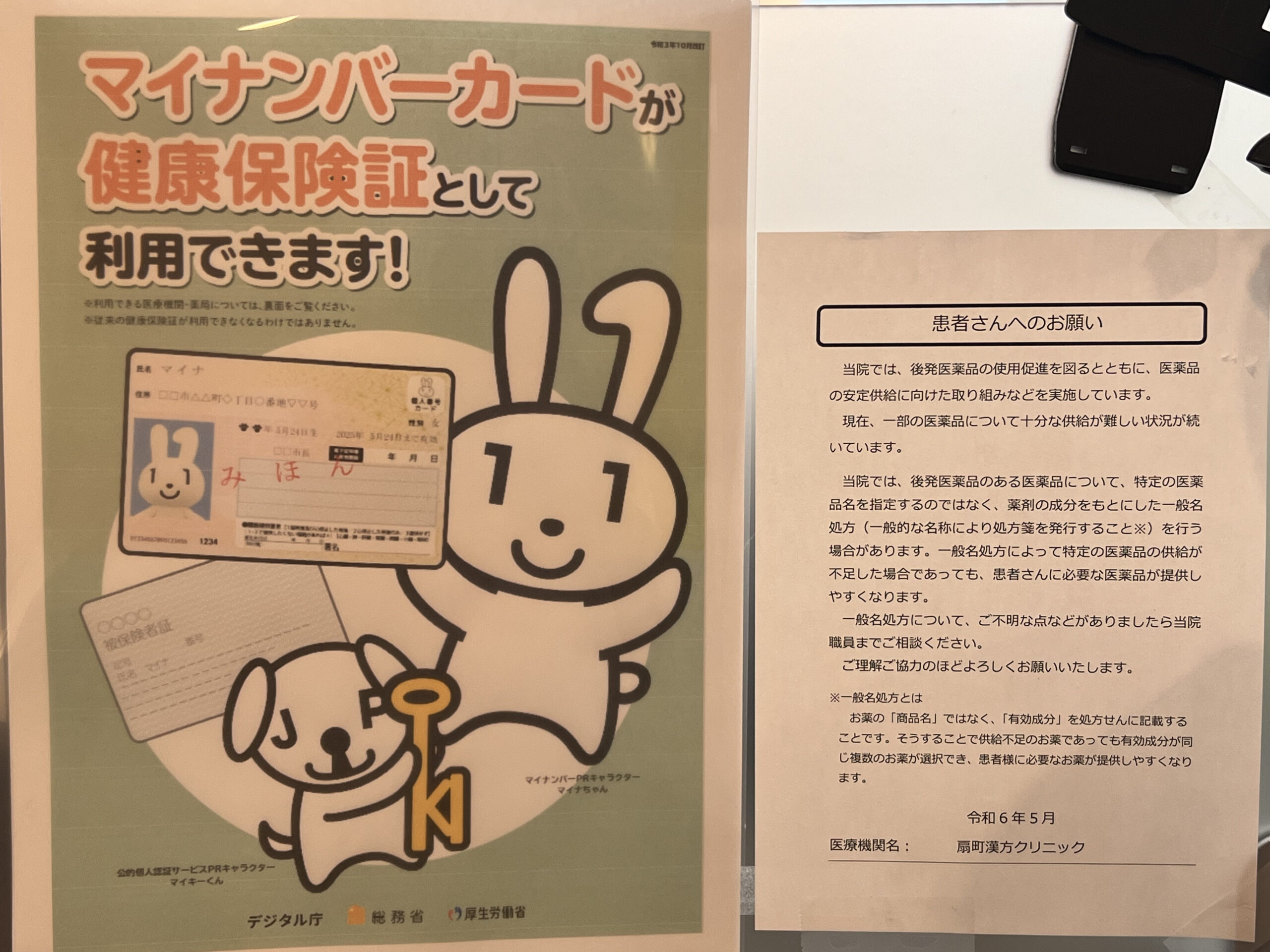



コメント