
こんにちは。扇町漢方クリニックの院長、大沢です。
「体質別セルフケアシリーズ」第7回は、《陰虚(いんきょ)》タイプです。
「夕方になると体がほてる」
「肌や喉が乾燥する」
「夜中に寝汗をかいて目が覚める」
こういったお悩みがある方は、《陰虚体質》かもしれません。
漢方ではこのような状態を「体を潤す“陰”が不足している」と考えます。
今回は、陰虚体質の特徴や原因、そして潤いを取り戻すためのセルフケア方法をご紹介します。
◆陰虚とは?~体の“潤い”と“冷却水”が足りない状態~
「陰(いん)」は体の水分、潤い、冷やす力などのこと。
「体質別セルフケア⑤ 湿痰タイプ」の記事で取り上げた「津液(しんえき)」が不足しているのが陰虚の特徴です。
また、「津液」のうち、「腎」に蓄えられているものを「腎陰」と言います。
「腎陰」は「生命力の蓄え」のようなもので、過度の活動はこの蓄えを消耗して「腎陰」が不足する陰虚の状態になります。
この陰が不足すると、体を適度に冷やしたり潤したりする力が弱まり、
「乾燥」「ほてり」「のぼせ」「寝汗」といった“内側からの熱っぽさ”があらわれるのです。
◆陰虚タイプの主な特徴
陰虚体質の方に見られる代表的な症状は以下の通りです
・顔や手足がほてる(特に夕方~夜)
・寝汗をかく、暑くもないのに汗ばむ
・喉や口が乾きやすい、肌もカサカサ
・便がコロコロしている、または便秘気味
・落ち着かず不安感がある、眠りが浅い
・舌の色が赤く、苔が少ないまたはない
「のぼせるのに冷たいものを摂りすぎると胃腸が弱る」など、“表面は熱いのに中は虚(足りない)”というのがこの体質の特徴です。
◆陰虚の原因になりやすい生活習慣
陰虚体質を招く主な要因は以下のとおりです。
- 睡眠不足や過労による消耗(とくに夜更かし)
- 辛いものや熱性の食材の過剰摂取(唐辛子、焼肉、アルコールなど)
- ストレスによる緊張状態の持続
- 加齢による自然な陰の減少(更年期以降に多い)
- もともとの体質(子どものころから痩せ型、肌や髪が乾燥しやすいなど)
陰虚の人は、“元気だけどすり減りやすい”という傾向があります。
◆今日からできる!陰虚のセルフケア
陰虚タイプのケアでは、「体に潤いを与える」「熱を冷ます」「消耗しすぎない」ことが大切です。
①潤いを与える食材を積極的に
中医学では「滋陰(じいん)」といって、体を内側から潤す食材を積極的に摂ります。
おすすめの食材
- 小麦、もち米、やまいも
- 蜂蜜、水あめ
- 白きくらげ、百合根、れんこん、豆腐、豆乳
- クコの実、黒ごま、松の実
- ほうれん草、小松菜、梨、すいか、みかん(潤しつつ冷ます)
- あわび、いか、
※胃腸が弱い人は冷やしすぎないよう、加熱調理で取り入れるのが◎です。
②睡眠と休息で「陰」を養う
陰は「夜」に回復されるため、夜の休息はとても重要です。
- 夜22時(遅くても23時)までに寝ることを心がける
- スマホや強い光は寝る1時間前からオフに
- ぬるめの湯船で副交感神経を優位にする
- 日中の軽い運動や日光浴で体内リズムを整える
③熱を助長する習慣を避ける
陰虚体質の方は、熱性の食材や負担のかかる生活習慣がさらに陰を消耗させてしまいます。
避けたいもの
- 唐辛子・こしょう・にんにくなどの辛味
- 強壮剤、朝鮮人参
- 焼肉・揚げ物・アルコールのとりすぎ
- 徹夜や過剰な運動、極度のストレス
“熱を入れすぎない” “潤いを守る”生活習慣がカギになります。
④体を潤し、熱を冷ます漢方薬の考え方
中医学では、陰虚に対して「滋陰清熱(じいんせいねつ)」という考え方で、
体に潤いを与えながら、内側にこもった熱をやわらげる処方を用います。
代表的な漢方薬
知柏地黄丸(ちばくじおうがん)
→ 陰を補う「地黄(じおう)」と、熱を冷ます「黄柏(おうばく)」「知母(ちも)」が配合されています。
ほてり、寝汗、口の乾き、尿の異常など、陰虚に“熱”が伴う場合に用います。
滋陰降火湯(じいんこうかとう)
→ 肺や胃の乾燥、のぼせ、喉の乾き、イライラなど、上半身に熱がこもる陰虚タイプに適しています。
麦門冬湯(ばくもんどうとう)
→ 喉や気道の乾燥、空咳、声枯れなど“肺の陰虚”に使われる処方です。
とくに乾燥した空気が苦手な方に向いています。
陰虚体質は、表面が熱くても、実は「内側が乾いて冷やす力が足りない」状態です。
漢方薬も「熱を冷ますだけ」ではなく、「潤す力を補う」視点で処方されます。
◆陰虚タイプへのメッセージ

陰虚の方は、割とよく動いて元気そうですが、持久力が足りない傾向があります。
また、寝不足や過労の方、夜型生活の方に多いです。
無理をせずに、陰の時間帯である夜は十分な休息をとりましょう。
ただ、その一方で、陽の時間帯である昼間は身体をよく動かすことが必要です。
適度な心地良い疲労感があることで、「腎陰」を補充するための睡眠をとりやすくなるのです。
ぜひ、陰と陽の意識を持って、その時間帯に相応しい生活を心がけてみてください。
次回はいよいよ最終回、「陽虚(ようきょ)タイプ」についてご紹介します。
「冷えやすい」「疲れやすい」「下痢をしやすい」などのお悩みがある方は、ぜひご覧ください。


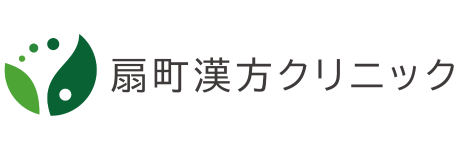
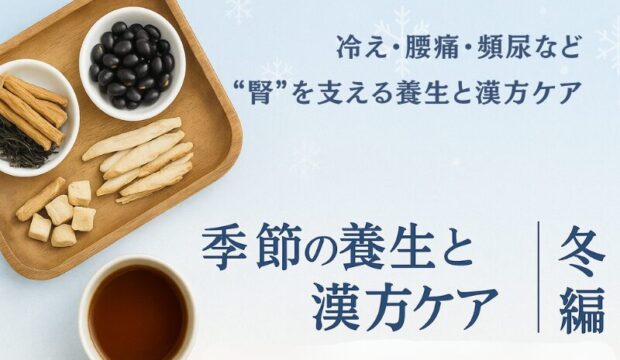


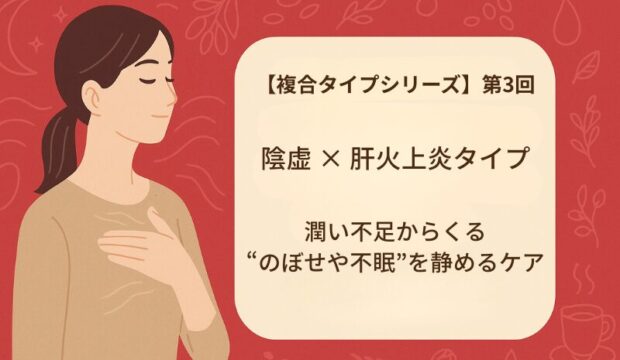
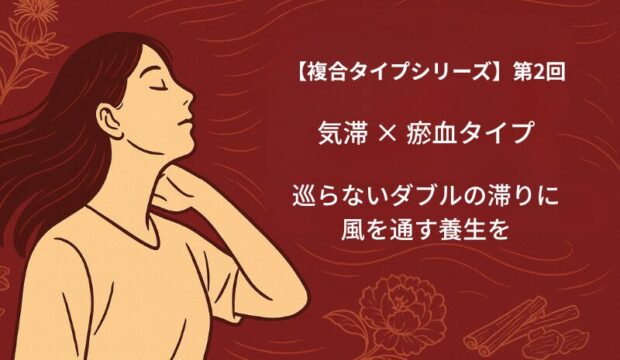







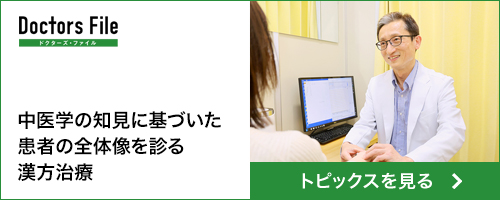
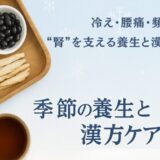








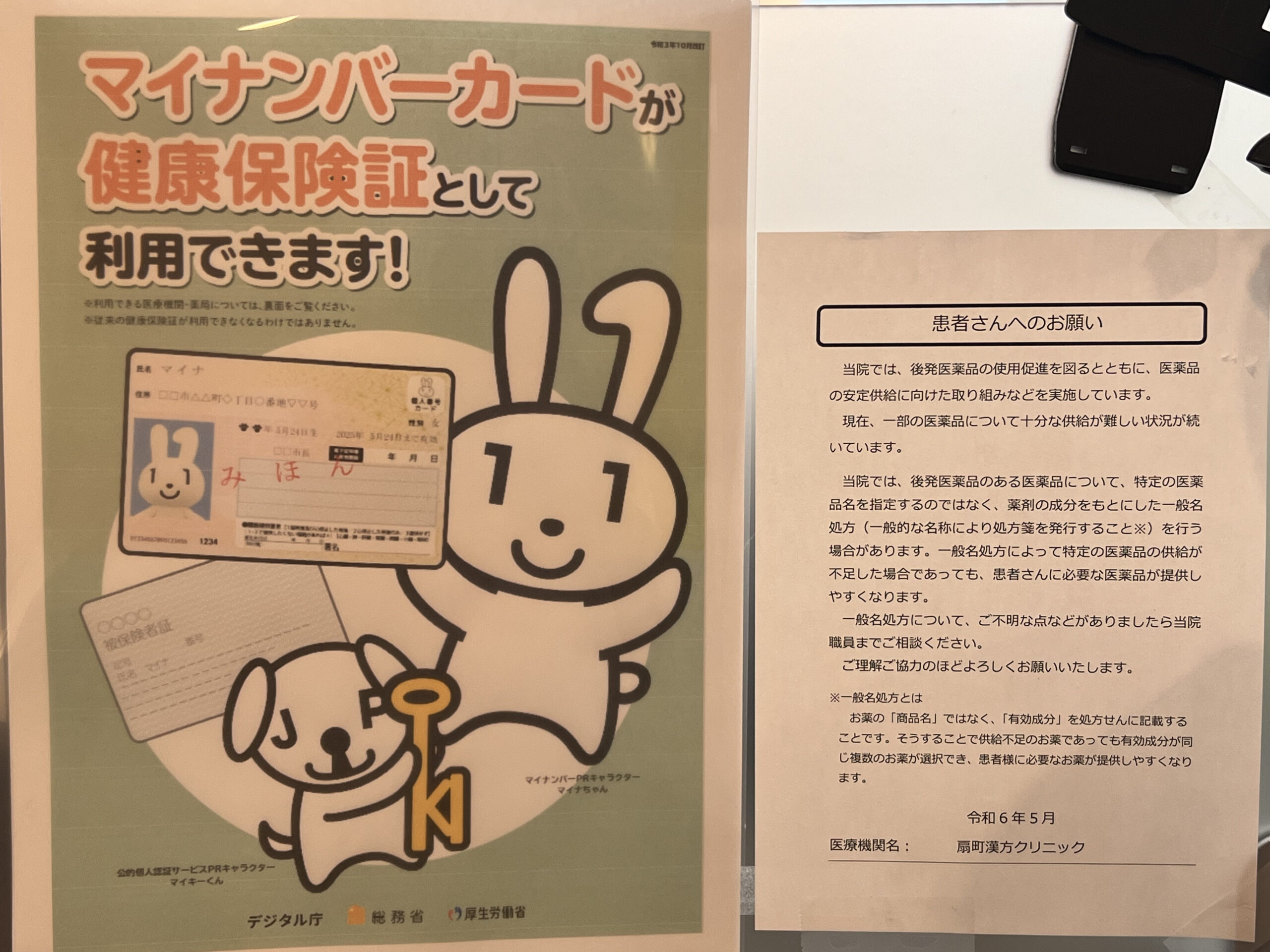



コメント