
こんにちは。扇町漢方クリニックの院長、大沢です。
今回は「体質別セルフケアシリーズ」第1回として、《気虚(ききょ)》タイプについてお話します。
「最近、なんとなく疲れが抜けない」
「食欲がない・多く食べられない」
「風邪をひきやすい」
「やる気が出ない」…
そんなお悩みがある方は、もしかすると《気虚》タイプかもしれません。
漢方では、この「気虚体質」を“エネルギーが足りていない状態”と捉えます。
この記事では、気虚の特徴や原因、日常から取り入れられるセルフケアまで、わかりやすくお伝えしていきます。
◆気虚とは?~体のエネルギーが足りない状態~
漢方でいう「気(き)」とは、目には見えませんが、心と体を動かす生命エネルギーのようなもの。
呼吸をしたり、食べたものを消化吸収したり、体温を保ったり…生きていくために欠かせない“元気のもと”です。
その「気」が不足している状態を「気虚(ききょ)」といいます。
まさに“エネルギー不足”の状態ですね。
「気」を作るために深く関わっているのが「脾(ひ)」で、「脾」の働きが低下して「気」が不足する状態を「脾気虚(ひききょ)」といい、これが気虚の代表的なものです。
◆気虚タイプの主な特徴
以下のような症状や傾向に当てはまることが多いです。
・疲れやすい、すぐに横になりたくなる
・食欲がない、食後に眠くなる、胃腸が弱い
・風邪をひきやすい、治りにくい
・声が小さい、話すとすぐに疲れる
・朝からだるい、やる気が出ない
・顔色が青白く、むくみやすい
・汗をかきやすく、ちょっと動いただけでもだるい
「頑張りたいのに、体がついてこない…」そんな感覚がある人に多いタイプです。
◆気虚の原因になりやすい生活習慣
気虚体質の背景には、次のような生活習慣や環境が影響しています。
・過労や睡眠不足 : 気は毎日“充電”されていくもの。休息不足では枯渇します。
・食生活の乱れ : 暴飲暴食や、冷たいもののとりすぎで消化機能が弱まると、気の生産が滞ります。
・運動不足 : 四肢(腕と脚)の運動不足で、「脾」(消化機能)が衰えて、気の産生能力が低下します。
・長引く病気 : 慢性的な病気によって、気が消耗されてしまう場合もあります。
◆今日からできる!気虚のセルフケア
気虚のセルフケアは、「気を補う(=補気)」ことと、「気を漏らさない(=気を守る)」ことがポイントです。
①胃腸をいたわる食事を意識
まずは、必要以上に食べないことが基本です。食欲もない状態で無理に食べると胃腸に負担がかかり、かえって「気」を損なうことになるので注意が必要です。
むしろ粗食で消化の良いものを中心にするのがお勧めです。「気」の多くは、食べたものから作られます。胃腸が弱ると「気」をうまく作れません。
おすすめの食材:
- うるち米、もち米、豆類(枝豆、えんどう、そら豆、大豆)、豆腐
- 山芋、さつまいも、じゃがいも、かぼちゃ
- 黒砂糖、氷砂糖、蜂蜜
- しいたけ、大根、りゅうがん
- アボガド、ココナツ、さくらんぼ、ぶどう
- うなぎ、えび、かたくちイワシ、かつお、かに、さけ、さば、さわら、さんま、たこ、ひらめ、ぶり
- 牛肉、かも肉、鶏肉、羊肉、豚肉
- うずら卵
- 甘酒
冷たい飲み物や食べ物・生ものは胃腸を冷やすので、控えめに。火の通った消化の良いものを主体にして、スープやおかゆで内臓を温めましょう。
②軽い運動と深呼吸
激しい運動よりも、まずはウォーキングやラジオ体操のような穏やかな運動が適切です。
また、深く呼吸することで、体内の「気」がめぐりやすくなります。
おすすめは、朝の散歩。朝日を浴びながら、ゆっくりと深呼吸すると、1日を気持ちよくスタートできます。
そして、次の段階として、可能であれば少し負荷を上げて「身体を適度に疲れさせる」運動ができれば理想的です。
身体には適応能力が備わっています。筋力トレーニングでも、負荷を増やすことで筋力を付ける必要性を身体が感じて筋肉が太く強くなります。ただ休むことも必要で、その休息期間に以前よりも強くなっていくのです(「超回復」と言います)。
そして「脾」は四肢(腕と脚)と関係が大きく、四肢の運動をすることで「脾」の強化につながります。つまり、気を補う力がつくことになるのです。
③睡眠の質を高める
しっかりと寝ることで、日中に消耗した「気」が回復します。
特に夜22時~2時の間は、「気」がもっとも回復しやすい時間。早めの就寝を心がけましょう。
- 寝る前のスマホは控えめに
- 部屋を暗くして、副交感神経が優位になる環境に
- 寝る1時間前のハーブティー(カモミールなど)も◎
④「気」を補う漢方薬の考え方
漢方薬には、体の中の「気」を補い、元気を取り戻す作用のあるものがいくつかあります。
ここでは、気虚体質によく用いられる漢方薬を、中医学の観点からやさしくご紹介します。
補中益気湯(ほちゅうえっきとう)
中医学では、「脾(ひ)」は“気を作る工場”のような役割があります。「肺」は気の巡りが生体の外へ漏れ出ないよう守る“バリア”としての機能があります。
この薬は、脾や肺の働きを高め、胃腸を元気にして消化吸収力を高め、同時に「気」を持ち上げる力(昇提作用)を助けます。
体がだるく、疲れやすい、食後すぐ眠くなる人におすすめされます。
六君子湯(りっくんしとう)
「脾胃(ひい)」の働きを整えることで、気の生産と循環を助ける薬です。気虚に加えて「痰(たん)」=余分な水分がたまっているタイプに向いています。
食欲がなく、胃が重い、ゲップや吐き気がある人に使われることがあります。
人参湯(にんじんとう)
胃腸の働きを高めて気を補う働きと、体の芯を温める働きがあるので、お腹が冷えて胃腸が弱っている状態の人に向いています。漢方薬は、同じ気虚でも「どこが弱っているか」「どのくらいの程度の虚か」などで処方が変わります。
自分に合った薬を選ぶためにも、ぜひ専門家にご相談くださいね。
◆気虚タイプへのメッセージ

気虚体質の方は「頑張り屋さん」や「責任感が強い」人が多く、つい自分のエネルギーを使い切ってしまう傾向があります。
でも、電池が切れては動けませんよね。
「ゆっくり休んで、ちゃんと食べる」ことは、自分を整えるための大切なケアです。
ぜひ、今日から少しずつ、あなたの気を補う生活を始めてみてください。
次回は「気滞タイプ」についてご紹介します。
「なんだかイライラ」「気分が沈む」…そんなお悩みがある方は、ぜひお楽しみに!


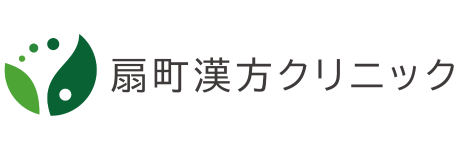
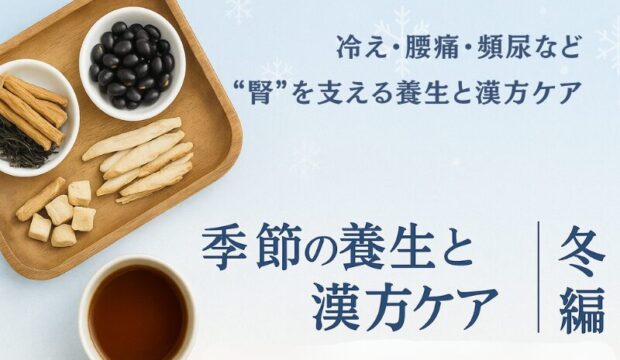


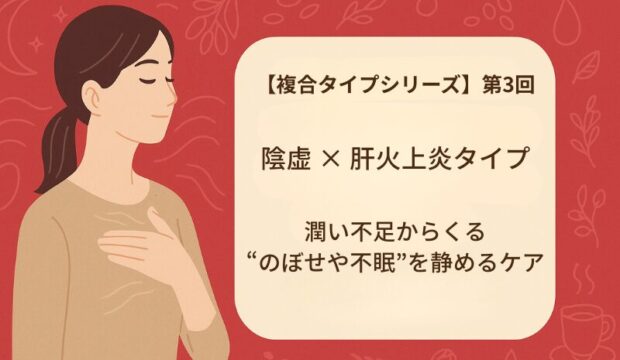
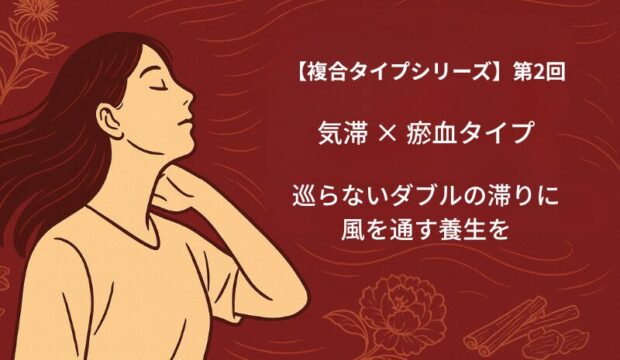








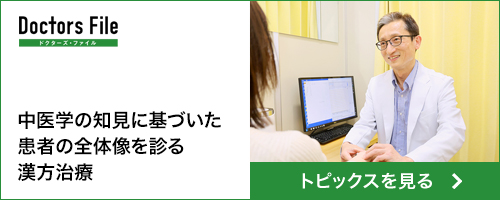
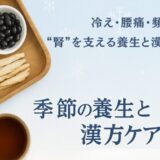








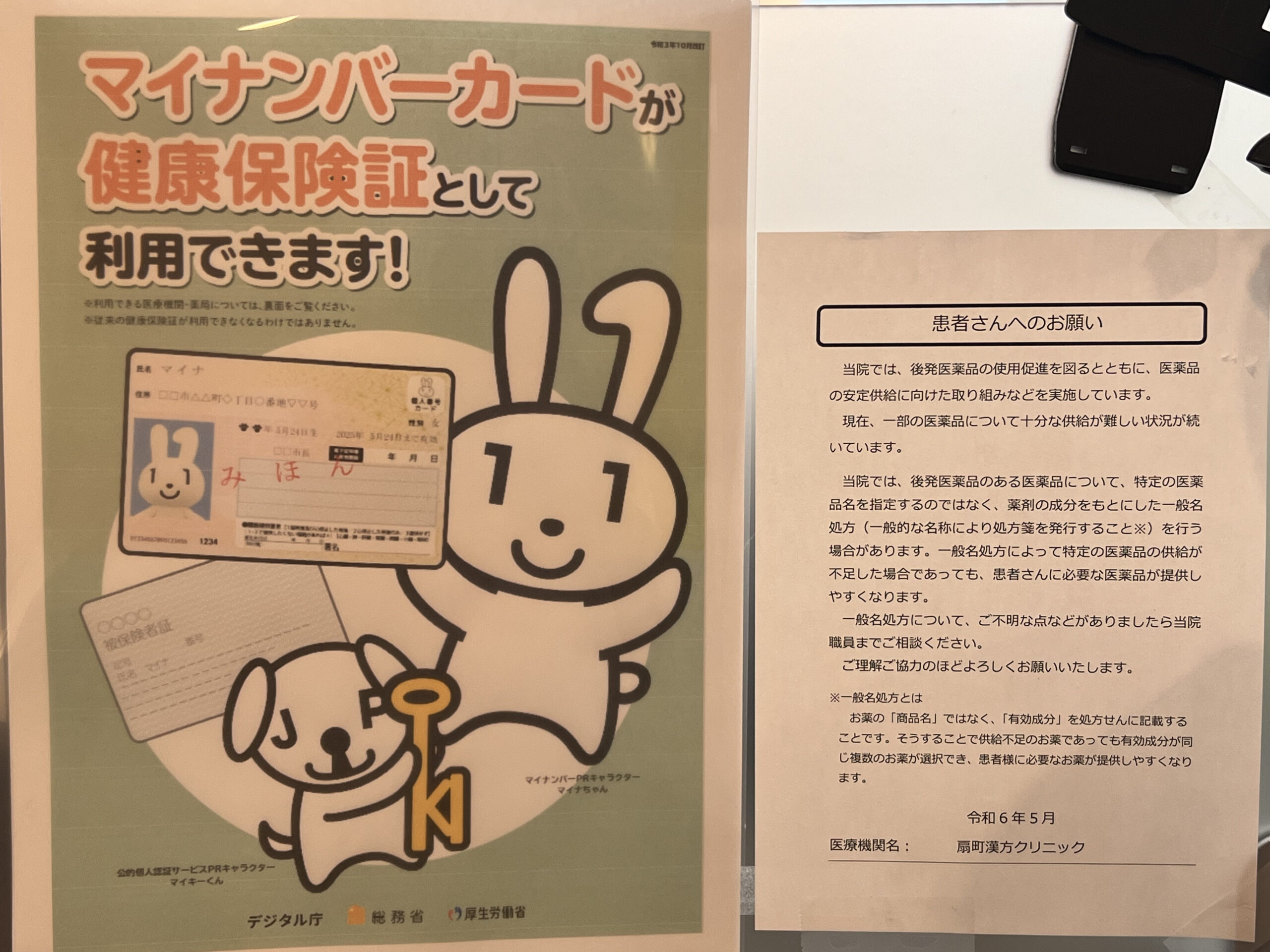



コメント