
こんにちは。扇町漢方クリニック院長の大沢です。
今回はイライラやストレス、肩こりなどに深く関係する“肝”についてお話ししますね。
気になる“心の揺れ”や体の不調、それ“肝”のサインかも?
・最近イライラしやすい
・ストレスがたまると、すぐに頭痛や肩こりが出てくる
・気分のアップダウンが激しくて、自分でもコントロールしづらい
そんなお悩みを抱えていませんか?
これらの症状、もしかすると東洋医学でいう“肝(かん)”の働きが乱れているサインかもしれません。
“肝”ってなに?とは、東洋医学から見た働き

東洋医学でいう「肝」は、西洋医学でいう一般的な“肝臓”だけを指すわけではありません。
もっと広い意味合いをもち、体と心の”めぐり”を助けてくれる大切な存在です。
「肝」はまるで交通整理をしてくれる存在のようなもので、体と心の流れがスムーズになるように助けてくれます。
具体的には:
・気(エネルギー)の流れをスムーズに保つ
・血液を全身にうまく巡らせる
・感情、特に“怒り”や“イライラ”と深く関係する
・目や筋肉、月経の調整にも関わる
そのため、「肝」がうまく働かなくなると、気持ちの浮き沈み、頭痛、目の疲れ、肩こり、月経トラブルなどが出てくることがあります。
特に女性は、ホルモンの変化と密接に関わっているため、“肝の不調”が出やすい傾向があります。
ストレス社会では“肝”が疲れやすい
現代は、気を遣うことも多く、知らず知らずのうちにストレスを抱えやすい社会です。
パソコンやスマートフォンの長時間使用による目の疲れ、感情を抑えこむ生活、過労や睡眠不足…。
これらはすべて、東洋医学でいうところの「肝」に大きな負担をかけます。
そして、「肝」のエネルギーが滞ると、気の流れが乱れて“気がめぐらない”状態に。
すると、怒りっぽくなったり、ため息が増えたり、緊張しやすくなったり…
心と体のバランスが少しずつ崩れていくのです。

イライラやため息が増えてきたら、“肝が疲れてるかも”と気づいてあげてくださいね。
こんな症状、ありませんか?
・ストレスがたまるとイライラしがち
・頭が重い、または頭痛が出やすい
・胃が張って苦しい感じがする
・夜に眠りづらくなる
これらは、「肝」の働きが乱れているときによくみられるサイン。
心と体のバランスが崩れ始めているかもしれません。
体質に合わせた漢方の考え方
🔸「巡りが悪くなっているタイプ」
→ 気持ちがふさぎやすく、ため息が多くなる方。
漢方では、気の流れをやさしく整えてくれる薬を使います。
🔸「火がたまっているタイプ」
→ 顔がほてりやすく、怒りっぽくなってしまう方。
この場合は、たまった“熱”を冷ましながら、心も落ち着かせる漢方薬を考えます。
🔸「潤い不足タイプ」
→ 目が乾きやすく、疲れやすい、爪が割れやすい…など。
これは、体の中の“栄養”が足りないサイン。潤いと栄養を補う処方を考えます。
“肝”の働きを整えるには?
POINT
1. ゆったりと深呼吸する時間を持つ
→ 呼吸を深くすることで、気の流れが整います。
2. “怒り”をためこまない工夫をする
→ 日記に書き出す、自然に触れる、誰かに話す…など、自分なりの方法で。
3. 目を酷使しすぎない
→ スマホ・パソコンを長時間見続けた後は、意識的に目を休めましょう。
4. 「緑の食材」や「酸味のあるもの」を取り入れる
→ セロリ、ピーマン、ほうれん草、梅干し、レモンなどは肝の働きを助けます。
心のバランスが崩れたら“肝”を疑ってみましょう
「肝」が整うと、気分が安定し、肩の力が抜け、全身のめぐりもスムーズになります。
まるで体の中に詰まっていたものがスーッと流れ出すような、心地よさをもたらします。
イライラや不安、目の疲れや肩こりが続くときは、無理に我慢せず、「今の自分、少し“肝”が疲れてるかも」と思ってあげてください。
そして、自然のリズムに寄り添いながら、心と体の流れを取り戻していきましょう。

当院では、ひとりひとりの体質に合わせた漢方薬やセルフケアのアドバイスを行っています。
気になる症状がありましたら、いつでもお気軽にご相談くださいね。


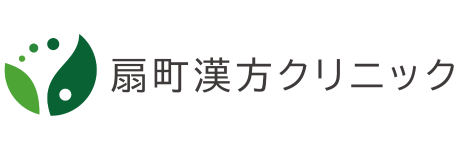
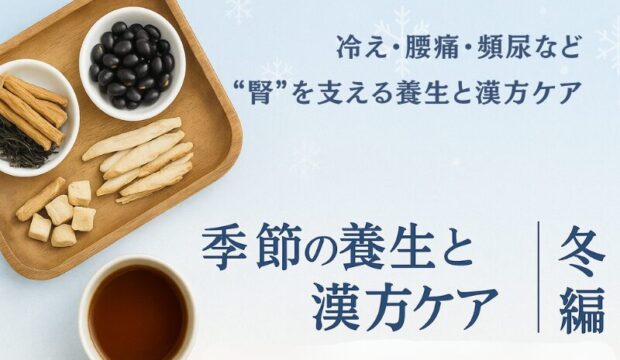


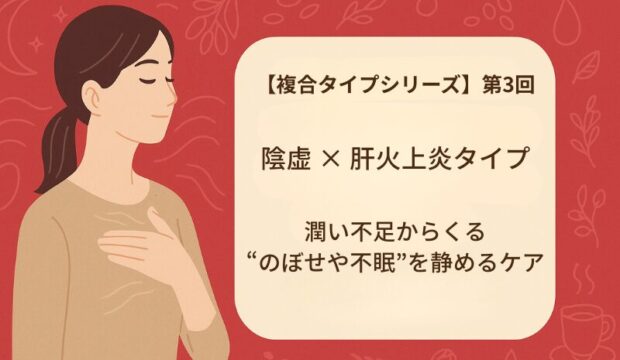
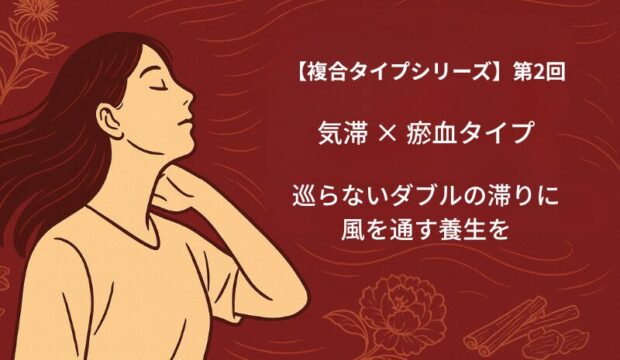








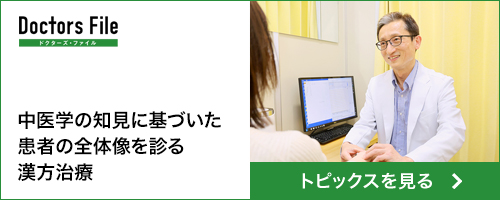
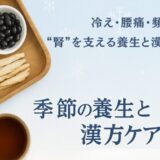








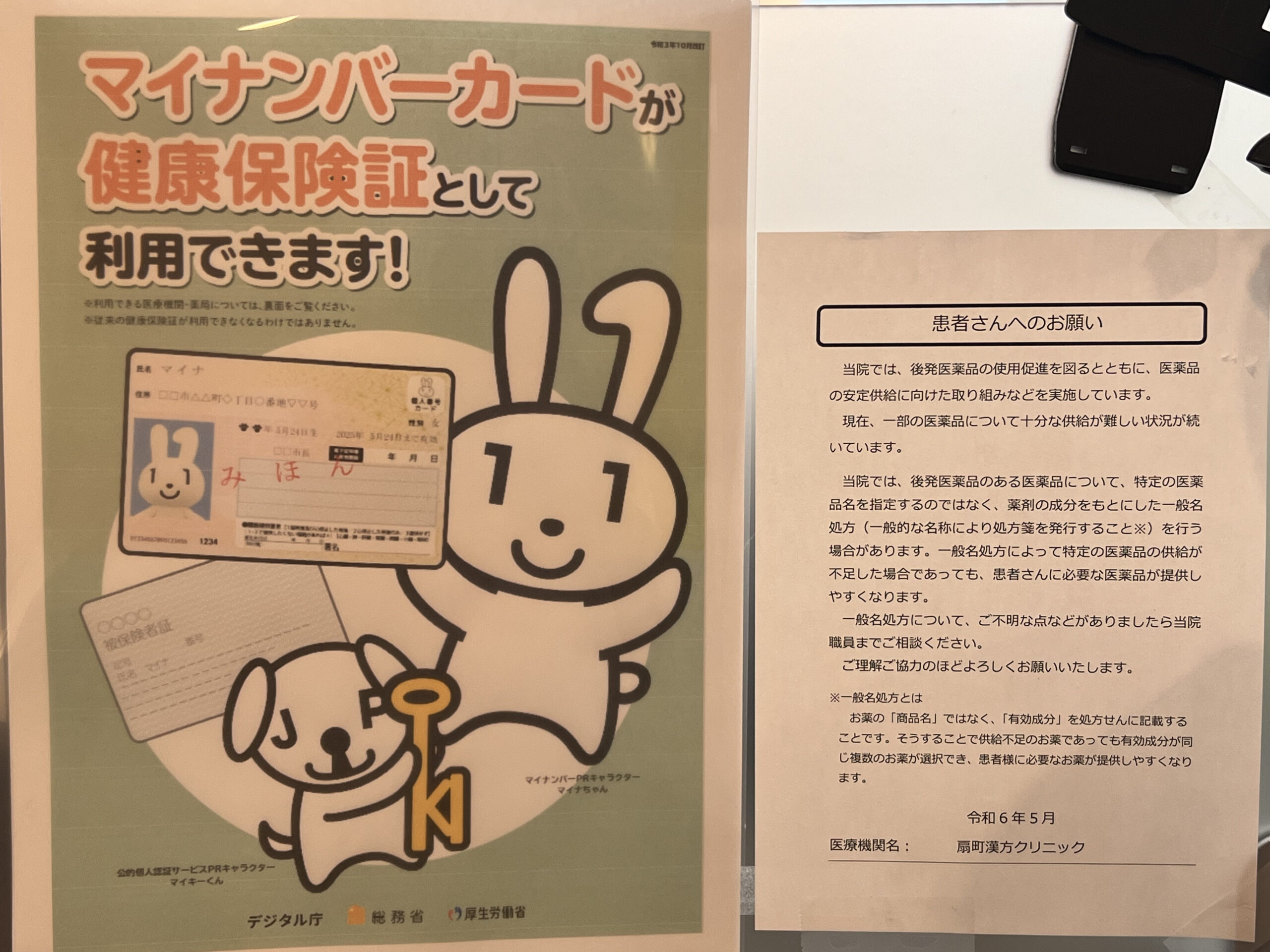



コメント